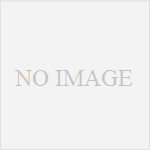立石寺(りっしゃくじ)は、山形県山形市にある天台宗の仏教寺院。山寺(やまでら)の通称で知られ、古くは「りゅうしゃくじ」と称した。詳しくは宝珠山阿所川院立石寺(ほうじゅさんあそかわいんりっしゃくじ)と称する。本尊は薬師如来。
蔵王国定公園(第2種特別地域)に指定されていて、円仁が開山した四寺(他は中尊寺・毛越寺、瑞巌寺)を巡る「四寺廻廊」を構成しているほか、若松寺と慈恩寺を含めて巡る出羽名刹三寺まいりを構成する。

歴史
創建
寺伝では貞観2年(860年)に清和天皇の勅命で円仁(慈覚大師)が開山したとされている。
当寺の創建が平安時代初期(9世紀)に遡ることと、円仁との関係が深い寺院であることは確かであるが、創建の正確な時期や事情については諸説あり、草創の時期は貞観2年よりもさらに遡るものと推定される。立石寺文書のうち『立石寺記録』は、「開山」を円仁、「開祖」を安慧(あんね)と位置づけており、子院の安養院は心能が、千手院と山王院は実玄が開いたとされている。

文化財
重要文化財
- 立石寺中堂(根本中堂)(建造物、明治41年(1908年)4月23日指定)正平年間(1346年から1370年)の再建と伝え、慶長13年(1608年)の大修理を含め数度の修理を受けているが、現在は慶長13年の姿を保っている。公開。
- 天養元年如法経所碑(考古資料、大正4年(1915年)3月26日指定)天養元年(1144年)8月18日に、真語僧入阿らが妙法蓮華経1部8巻を書写して、霊崛のほとりに納めた旨が記されている。非公開。
- 立石寺三重小塔(建造物、昭和27年(1952年)7月19日指定)塔頭華蔵院境内の右側の岩壁に南面して掘られた岩屋の内にある、高さ2.5mの木造小塔。相輪に永正16年(1519年)の銘があることから、その頃に造立されたものと思われる。公開。
- 木造薬師如来坐像(彫刻、昭和44年(1966年)6月11日指定)膝部裏から元久2年(1205年)の修理銘が発見され、平安時代の作とされる。桂の一木造。秘仏、非公開。
- 木造慈覚大師頭部 1箇・木棺 1合(附:木造五輪塔、元和四年木札、貞享四年木札)(彫刻、平成18年(2006年)6月9日指定)平安時代前期の製作と推定される非公開。
国の名勝・史跡


交通アクセス
石段は1015段ある。
寺の東にある千手院観音と、かつて山伏の修行場であった垂水遺跡を経由する山道もあり、「裏山寺」「峯の浦」と称されている。